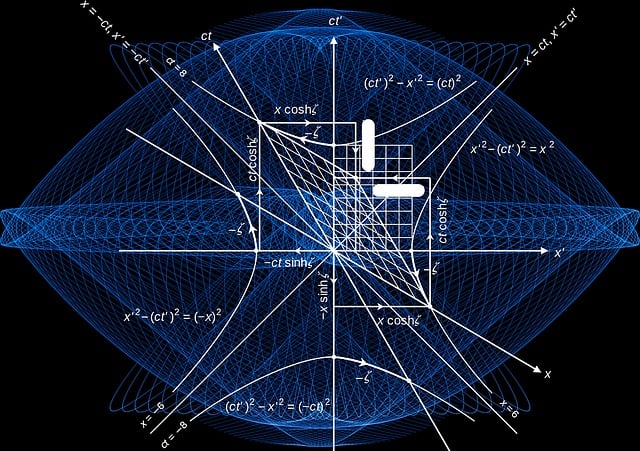2025年京大 数学 第4問 は空間ベクトルの問題です。問題文は以下のとおりです。
座標空間の 4 点 O, A, B, C は同一平面上にないとする.s, t, u は 0 でない実数とする.直線 OA 上の点 L,直線 OB 上の点 M,直線 OC 上の点 N を
\overrightarrow{OL} =s \overrightarrow{OA} ,\overrightarrow{OM} =t \overrightarrow{OB} ,\overrightarrow{ON} =u \overrightarrow{OC} が成り立つようにとる.
(1) s, t, u が \displaystyle\frac{1}s + \frac{2}t +\frac{3}u = 4 を満たす範囲であらゆる値をとるとき,3 点 L, M, N の定める平面 LMN は,s, t, u の値に無関係な一定の点 P を通ることを示せ.さらに,そのような点 P はただ一つに定まることを示せ.
(2) 四面体 OABC の体積を V とする.(1) における点 P について,四面体 PABC の体積を V を用いて表せ.
ちょっと見慣れないシチュエーションで焦りますが、定義に従って丹念に考察していけば案外何とかなるかもしれません。面倒くさい計算が出てこなさそうなのも良い感じです。それでは見ていきましょう。
2025年京大 数学 第4問 小問1の解法
平面 LMN をベクトルで表現する
まず、O, A, B, C は同一平面上にないという条件から、 \overrightarrow{OA} , \overrightarrow{OB} ,\overrightarrow{OC} が一次独立であることがわかります。実際、これらの3ベクトルが一次独立でないなら、 \overrightarrow{OA} は他の2ベクトルの線形和で表されるので、4点 O, A, B, C はその2ベクトルが張る平面上にあることになります。
\overrightarrow{OA} , \overrightarrow{OB} ,\overrightarrow{OC} が一次独立なので、 \overrightarrow{OL} , \overrightarrow{OM} ,\overrightarrow{ON} も一次独立です。もし \overrightarrow{OL} が \overrightarrow{OM} ,\overrightarrow{ON} の線形和で表現されるなら、 \overrightarrow{OA} も \overrightarrow{OB} ,\overrightarrow{OC} の線形和で表現されてしまうからです。
このとき、平面 LMN 上の任意の点 P は、 x + y + z = 1 を満たす実数 x,y,z が一意に存在して
\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OL} +y\overrightarrow{OM} +z \overrightarrow{ON} とベクトル表記できます。
このことは学校であまり取り上げていないかもしれませんが、2点 L,M を通る直線上の点 P がx + y = 1 を満たす実数 x,y によって
\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OL} +y\overrightarrow{OM} と一意に表記できることからアナロジカルに連想できるでしょう。
実際、平面 LMN は2つのベクトル \overrightarrow{LM} ,\overrightarrow{LN} によって張られるので、 LMN の任意の点 P は適当な実数 x,y によって
\overrightarrow{NP} = x\overrightarrow{NL} +y\overrightarrow{NM} と一意に表記できます。したがって
\begin{aligned}
\overrightarrow{OP} & = \overrightarrow{ON} +\overrightarrow{NP}\\
&= \overrightarrow{ON} + x\overrightarrow{NL} + y\overrightarrow{NM} \\
& = \overrightarrow{ON} + x(\overrightarrow{OL} -\overrightarrow{ON} ) + y(\overrightarrow{OM}- \overrightarrow{ON}) \\
& = x \overrightarrow{OL} + y \overrightarrow{OM} + (1 -x-y ) \overrightarrow{ON}
\end{aligned}です。ここで z = 1 – x – y と置けば、 x + y + z = 1 かつ
\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OL} +y\overrightarrow{OM} +z \overrightarrow{ON} です。
題意を満たす P の存在を証明する
ここでs, t, u が満たす変な条件 \displaystyle\frac{1}s + \frac{2}t +\frac{3}u = 4 が、和が定数であることに着目しましょう。なんか、 x + y + z = 1 に似ていませんか。和が1でなくて4ですが、そんなことは4で割ってしまえばOKです。
そこで
x = \frac{1}{4s}, y = \frac{1}{2t}, z = \frac{3}{4t}と置くと、 x + y + z = 1 なので
\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OL} +y\overrightarrow{OM} +z \overrightarrow{ON} で定義される P は LMN 上の点で、しかも
\begin{aligned}
\overrightarrow{OP} = & \frac{1}{4s} \cdot s\overrightarrow{OA} +\frac{1}{2t} \cdot t\overrightarrow{OB} +\frac{3}{4u} \cdot u \overrightarrow{OC} \\
= & \frac{1}{4} \overrightarrow{OA} +\frac{1}{2} \overrightarrow{OB} +\frac{3}{4} \overrightarrow{OC}
\end{aligned}と、明らかに s,t,u と無関係です。以上、題意を満たす P の存在は思いの外あっさり証明できました。
題意を満たす P の一意性を証明する
セオリー通り、背理法で攻めてみましょう。
先程存在を証明した P とは異なる点 Q が存在して、平面 LMN はs, t, u の値に関わらず Q を通るものとします。
Q は平面 LMN 上の点なので、各s, t, u に対して p + q + r = 1 を満たす実数 p,q,r が一意に存在して
\overrightarrow{OQ} = p\overrightarrow{OL} +q\overrightarrow{OM} +r \overrightarrow{ON} が成り立ちますが、 Q はs, t, u の値に関わらず固定的な点なので、s, t, u の値に無関係な実数 a,b,c が存在して、s, t, u の値に関わらず
\begin{aligned}
\overrightarrow{OQ} &= p\overrightarrow{OL} +q\overrightarrow{OM} +r \overrightarrow{ON} \\
& = sp\overrightarrow{OA} +tq\overrightarrow{OB} +ur \overrightarrow{OC} \\
& = a\overrightarrow{OA} +b\overrightarrow{OB} +c \overrightarrow{OC} \\
\end{aligned}が成り立ちます。
したがって、 \overrightarrow{OA} , \overrightarrow{OB} ,\overrightarrow{OC} が一次独立であることから明らかに
sp=a,tq=b,ur=c
すなわち
p = \frac{a}s,q = \frac{b}t, r= \frac{c}uが成り立ちます。
p + q + r = 1 であったので、
\frac{a}s + \frac{b}t + \frac{c}u = 1 \cdots (1)です。
一方、問題文の条件 \displaystyle\frac{1}s + \frac{2}t +\frac{3}u = 4 から
\frac{1}{4s} + \frac{1}{2t} + \frac{3}{4u} = 1 \cdots (2)ですが、式(1)も式(2)も平面の方程式っぽいです。そこで
x = \frac{1}s, y = \frac{1}t,z = \frac{1}uと変数変換すると、式(1)および式(2)からそれぞれ平面の方程式
\begin{aligned}
& ax + by + cz = 1 \cdots (3) \\
&\frac{1}4 x + \frac{1}2 y + \frac{3}4 z = 1 \cdots(4)
\end{aligned}を得ます。
式(3)が表す平面を H 、式(4)が表す平面を I と置くと、式(2) を満たすすべての s,t,u に対して式(1) が成り立つということは、 平面 I 上のxyz ≠ 0 であるすべての点が平面 H 上にあるということと同義(つまり言い換え)です。
ところが、Q は P と異なる点なので
(a,b,c) \ne (\frac{1}4,\frac{1}2,\frac{3}4)であり、したがって H と I は異なる平面ですが、異なる2平面は全く交点を持たないか、交線を1本だけ持つかのいずれかなので、これは矛盾です。
以上、題意を満たす P は1つしかないことが証明できました。
2025年京大 数学 第4問 小問2の解法
四面体 OABC と四面体 PABC の体積比を求めよというのがお題ですが、2つの四面体の底面 ABC が共通なので、 O および P と ABC との距離がわかればOKです。
各点の座標がわからないので、平面に垂らした垂線の長さなど求められるのかよ、とも思いますが、まず P がどこにあるのかを考えてみましょう。
\begin{aligned}
\overrightarrow{OP} = \frac{1}{4} \overrightarrow{OA} +\frac{1}{2} \overrightarrow{OB} +\frac{3}{4} \overrightarrow{OC}
\end{aligned}であったので、
\frac{1}4 + \frac{1}2 + \frac{3}4 = \frac{3}2 > 1であることから P が平面 ABC 上にないことがわかりますが、ある点 X が平面 ABC 上にある必要十分条件は x + y + z = 1 を満たす実数 x,y,z が一意に存在して
\begin{aligned}
\overrightarrow{OX} = x \overrightarrow{OA} +y \overrightarrow{OB} +z \overrightarrow{OC}
\end{aligned}であったので、ベクトル \overrightarrow{OP} に \displaystyle\frac{2}3 をかけたら平面 ABC 上に乗るんじゃね、と思いつければ勝ちです。
すなわち点 D を
\overrightarrow{OD} = \frac{2}3\overrightarrow{OP} で定義すると、 D は平面 ABC 上の点でかつ、線分 OP を 2:1 に内分します。
よって O および P と ABC との距離の比も 2:1 であり、四面体 PABC の体積は四面体 OABC の半分の
\frac{1}2 Vです。
解法のポイント

小問1は s,t,u に関する条件が LMN 平面上に存在するための必要十分条件に転化できることに気が付くことが全てです。条件が s,t,u の逆数で表現されていることも大きなポイントで、 \overrightarrow{OA} , \overrightarrow{OB} ,\overrightarrow{OC} のそれぞれにかかっている s,t,u をキャンセルできるのではないか、と気がつけるための大きなヒントになっています。
もしこれに気がつけなかったとしても、式(1)および式(2)が任意の s,t の恒等式と解釈することによって、多少計算量は増えますが答えにたどり着くことは可能です。
小問2は本稿で示したとおり、線分 OP と 平面 ABC の交点を簡単に導出できることに気がつければ、ソッコー答えが得られます。空間図形に対する感覚を鋭くするよう、日頃から心がけましょう。