千葉県立高校入試 数学の傾向と対策
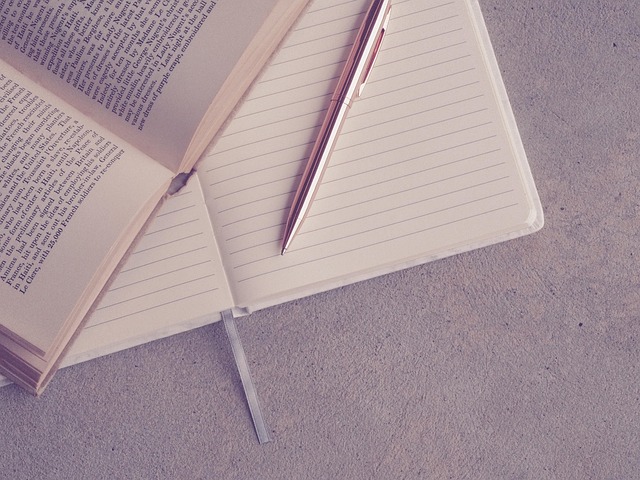
数学に関する 千葉県立難関高入試 の傾向と対策です。印西市、白井市から、県立千葉、県立船橋、東葛飾、千葉東、市立千葉、薬園台、佐倉の各高校を受験することを想定しています。
入試問題の傾向
2022年度から、試験問題の傾向が大きく変わりました。以前は5問構成だったのが、以下のように4問構成になっています。
| 年 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 計算問題 | 二次関数 | 図形 | 円錐と最小公倍数 |
| 2024 | 計算問題 | 二次関数 | 図形 | 一次関数 |
| 2023 | 計算問題 | 一次関数 | 図形 | 不定方程式の整数解問題 |
| 2022 | 計算問題 | 二次関数 | 図形 | 一次関数 |
2022年に出題傾向が変わってしばらくは出題パターンがいろいろ動いていましたが、最近は傾向が固まってきました。特徴としては、変にひねくれたところがなく、基礎的な出題でありながら、無理のない範囲で思考力を問う問題になっているところです。公立高の出題内容として、妥当なところに近づいていると言えます。
第4問は例年さまざまな趣向が凝らされています。見慣れない出題内容なので面食らいますが、1番難しい問題というわけではないので、あわてず落ち着いて対処すれば大丈夫です。
例年必ず出題されていた、他の問題とは難易度レベルが大きく乖離した超絶難問(拘泥しすぎると時間を空費してえらいことになるので、筆者はこれをポイズンピル問題と呼んでいます)は、昨年に引き続いて今年もありませんでした。難しい問題は「思考力を問う問題」で、ということかもしれません。
2022年以降の出題傾向を以下のリンク先に記述してありますので、ご覧ください。
2021年以前は以下のように5問構成でした。
| 年 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 計算問題 | 計算問題 | 2次関数 | 図形 | 整数 |
| 2020 | 計算問題 | 計算問題 | 2次関数 | 図形 | 整数 |
| 2019 | 計算問題 | 計算問題 | 2次関数 | 図形 | 体積 |
| 2018 | 計算問題 | 計算問題 | 2次関数 | 図形 | 整数 |
| 2017 | 計算問題 | 計算問題 | 2次関数 | 図形 | 整数 |
大きな特徴としては、第5問に整数の規則性に関する問題が出ていたことです。数の規則性については、最近は思考力を問う問題の方で出題されています。学校で体系的に習わないので独自の対策が必要ですが、以下の問題集を履修すると力がつくでしょう。
また、ポイズンピル問題は第4問に出題されていました。
各設問の時間配分

試験時間は50分です。大問が4つあるので、各問に10分ずつ配分し、残り10分を見直しおよび予備の時間とするのが理想的な時間配分です。
この時間配分を前提とするとき、大問1は1小問当たり、平均45秒程度で解く必要があります。簡単だからと悠長に構えていることはできません。タイムアタック的にどんどん解くことが求められます。
また、ポイズンピル問題には5分程度しか時間が取れないでしょう。拘泥しすぎて自滅しないよう、最初の一睨みで回答方針を見抜く、といった瞬発力が求められます。
目標得点
印西市、白井市は4学区なので、学区内の佐倉高校のほか、隣接する1学区の県立千葉/千葉東/市立千葉、2学区の県立船橋/薬円台、3学区の東葛飾の各高校が受験可能です。
各校ごとの数学の目標得点は以下の通りです。
県立千葉/県立船橋/東葛飾
このクラスの学校は、各科目の平均が90点以上必要と言われています。したがって、数学が得意でない人も90点は取りたいところですし、数学が得意な人は満点と言いたいところですが、ポイズンピルがある場合を考慮して95点以上が目標となります。1問当たりの平均配点が5点なので、ロスは2問以内です。
千葉東/市立千葉/佐倉/薬園台
このクラスの学校は、各科目の平均が80点以上必要と言われています。したがって、最低でも80点、出来れば90点以上が目標となります。ロスは4問以内です。
受験対策

印西市、白井市の公立中学校からから難関千葉県立高校を目指す場合の対策ですが、入試問題が基本タイムアタックなので、問題を早く正確に解くことが主要な目標になります。
平素の学習について
学校の授業の進度に合わせて、該当範囲の問題をたくさん解くことがポイントです。これで速さと正確さを養います。
使用する問題集は解説重視のものより、問題数が多いものが良いと考えています。ポイントは目標解答時間が設定されていることです。同じ問題集を何度も繰り返し解いて、力をつけてもらいますが、1回目は目標時間内に解くことを目指し、2回目以降は目標次男の7割以内とか5割以内と言うように、解く時間を短くしていきます。
使用を想定している問題集は、以下の通りです。
ハイクラステストのほうが、やや難しくなっています。学力に応じて使い分けることになりますが、両方使用してもよいでしょう。
先取り学習について
入試で必須の円が絡む図形問題、3平方の定理、2次関数は、公立中学校の授業では3年次の2学期からの登場となり、これを待って勉強を開始するのでは入試に間に合いません。
そこで2年次の後半あたりから先取り学習を開始し、3年次の遅くとも夏休み明けまでには、基本的な問題が解けるようにしていきます。
先取り学習は学習塾または家庭教師の利用が前提になります。独学でも何とかならないわけではありませんが、誰かに教わったほうが、効率よく学習を進められるでしょう。
思考力を問う問題への対策
こちらにまとめてありますので、是非ご覧ください。
受験勉強でお困りのことがあれば㈲峰企画にご相談ください
以上が県立高校受験の傾向と対策となりますが、もし「具体的な勉強の仕方がわからない」とか「応用力が身につかない」と言ったお悩みをお持ちの際は、当社の家庭教師にご相談ください。実際に難関校を突破した実績、ノウハウと、難問解法の知見によって、お悩みを解決いたします。以下のリンク先をご覧ください。
家庭教師無料体験授業実施中
無料の体験授業を実施中です。以下のフォームから、お気軽にお申し込みください!また、お電話でのお申し込みも承ります。





