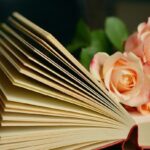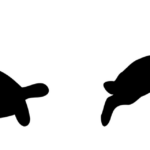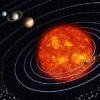公立から東大に行こう!

当社の売り、「公立の中高から塾なしで東大に入る」方法です。当社サイトの各所に記述がありますが、改めてまとめてみます。数学を念頭に記述していますが、基本的に他の科目も同じです。教材名を適宜置き換えてお読みください。
公立中学校で学年トップを目指す
「そんなことができれば苦労はないぜ」と思われると思いますが、渋幕ならともかく普通の公立中なら結構何とかなります。
方法は至って単純です。
- 学校の授業と教科書を完全に理解する
- 受験研究社「標準問題集」をやりこむ
たったこれだけです。公立高校の入試は教科書の範囲からしか出題されないので、塾とかでアドバンストな勉強をする必要はありません。
あとは①と②が本当にできるかですが、まず①です。
授業は集中して聴く
授業は集中して聴きましょう。一こま50分というのは結構長く、その割に教える内容は少ないので時間的余裕があります。その場で理解するよう努めましょう。少しでもわからなことがあればすかさず質問してください。
数学の教科書には例題が載っているので、授業を聴いて少しわかったらその場で試しに解いてみましょう。本当に理解できているかどうかが即時にわかります。
あと、ノートはきちんと録りましょう。記憶を定着させるには文字を書くことが非常に有効です。
問題集はできるようになるまで反復する
②については、これは文字通りやるだけです。標準問題集は標準回答時間が設定されているので、その時間内に解けるよう頑張りましょう。
あとは反復です。定期テストまでにその範囲分を2回はやって、完全に解けるようにしましょう。
使用する問題集は同程度の難易度であればお好みに応じてチョイスして構いませんが、いろいろな問題集をたくさん用意するのはどうせやりきれないので、やめましょう。また、やたらに難しい問題集も、特に学年が若いうちは避けたほうが良いでしょう。
勉強時間は学年+1
勉強時間は平日は学年+1くらいで十分です(1年なら2時間、2年なら3時間)。試験の2週間位前からこれに1時間プラスしてください。
休みの日は4,5時間は確保するようにしましょう。
上記がきちんとできれば、マジで定期テスト満点が取れます。満点ということはそれより上がないので、必然的にトップです。ここまではやれば必ずできます。
高校でも成績上位を目指す
中学で学年トップクラスなら、公立高校はどこでも好きなところに入れます。県千葉、東葛、県船橋など、毎年複数人の東大合格実績がある学校を狙いましょう。
高校でも勉強方針は基本的に中学と同じです。
- 授業には何が何でも食らいついていく
- まずは標準問題集から始めて、緑チャート→赤チャートとステップアップ
高校でも授業が基本
県立であっても進学校なら独自のノウハウでカリキュラムを組んでいるので、基本的に学校の授業だけで東大を狙えます。その分内容が高度で進度も速いので、とにかく振り落とされないように食い下がってください。
標準問題集に加えて緑チャートをやる
また、数学の場合は緑チャートあたりが副教材として与えられることがあるので、普段使いの問題集に加えてこれをやり込んでください。緑チャートクラスだとたまに難問が混じっていて、そういうものは初見では解けませんが、解説をよおく読んで理解に努めてください。
緑チャートから赤チャートに移行する
標準問題集と緑チャートをやり込んで、標準問題集はちょっとゆるいかなと感じられるようになったら、力がついた証拠です。成績上位クラスが狙えるので、学年で20位以内くらいを目指しましょう。
緑チャートもゆるいかなと感じられるようになったら、いよいよ赤チャートへ移行します。内容がだいぶハードですが解説が詳しいので、緑チャートが使いこなせていれば大丈夫です。
仕上げに難問集とジャンル別問題集
高校3年位になったら、難問集を買って本番に備えましょう。もちろん赤本は必須ですが、別の学校の難問をやることで応用力が付きます。ただし難問集ばかりやると調子を崩すので、気をつけましょう。
また、必要に応じてジャンル別の問題集を使うのも有効です。筆者は数列と複素数の問題集を使っていましたが、これでだいぶ力が付きました。苦手な分野があればこの手の問題集で補強しましょう。
勉強時間は平日4〜5時間
家での勉強時間は平日4〜5時間、試験前なら6時間程度確保しましょう。休みの日は8〜10時間程度は勉強しましょう。
ポイントは集中力
中学校の時点から上記のように勉強を進めていけば、東大であってもボーダーラインからかなりの余裕を持って合格できます。塾も家庭教師も、中高一貫校も不要です。
ただ、「そんなのはただの画餅では」とのご指摘があるとすれば、それはごもっともです。
この手のハウツーものが画餅に帰すか否かは、ひとえに勉強する集中力にかかっています。勉強時間だけ確保しても中身がなければ、当然効果は出ません。
集中力の度合いは試験時を100としたときに、60から70は欲しいところです。集中できているかどうかは単位時間に解く問題数でベンチマークすることができます。
そんな集中力は当然長く持続できませんので、短い時間で効率よく勉強することがコツです。
集中力をどのように持続するかについては、稿を改めます。
勉強に関するご相談は峰企画へ

「勉強のやり方をもっと具体的に知りたい」「どうしてもわからないところがあるので補習してほしい」など、勉強に関するご相談は峰企画へ。以下の電話番号にお気軽にお問い合わせください。
また、峰企画では無料の家庭教師体験授業を実施しております。「家庭教師など不要だ」などと見栄を切った手前アレですが、やはり定期的に勉強を見て欲しいといった場合にはお気軽にお申し込みください。もちろん、しつこい勧誘などあとぐされは一切ございません。